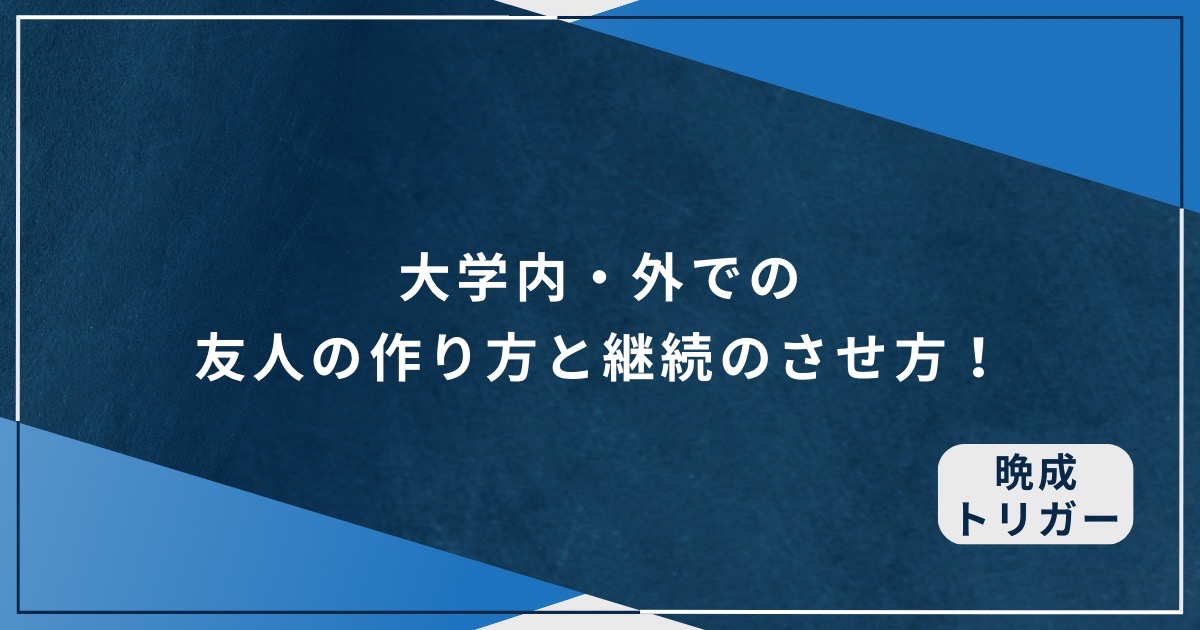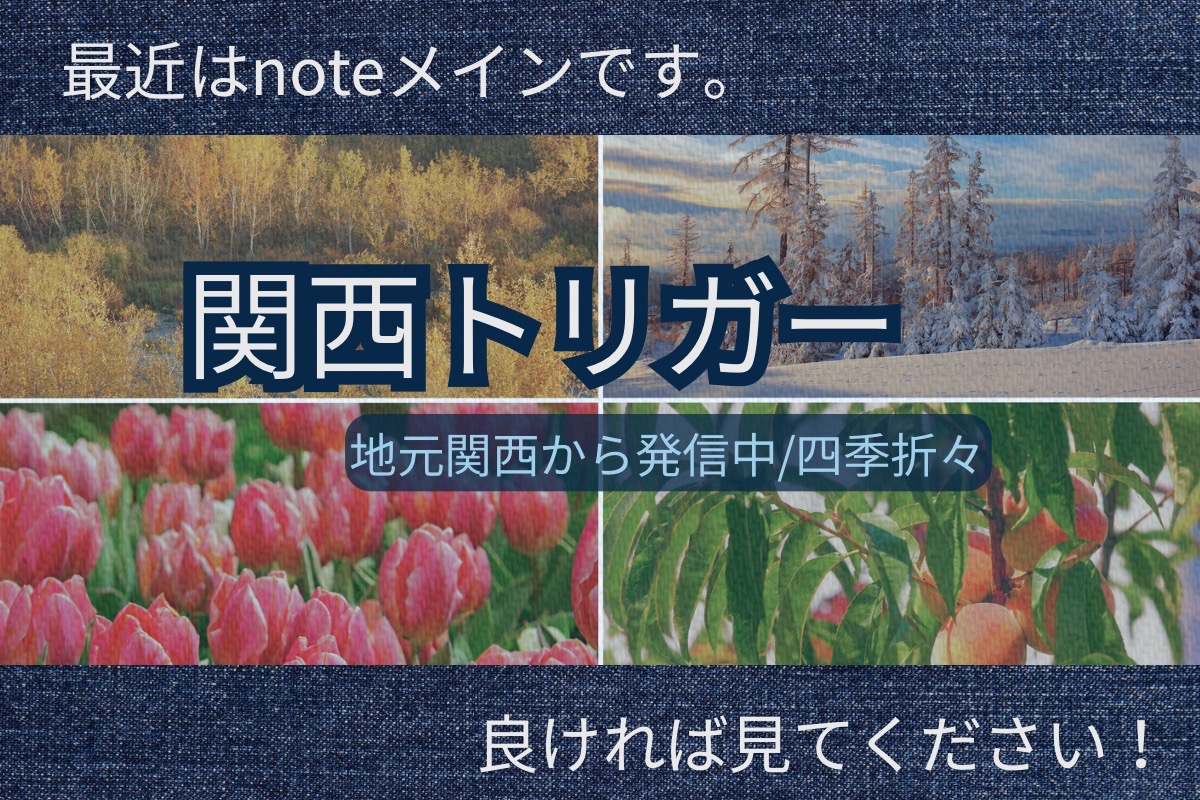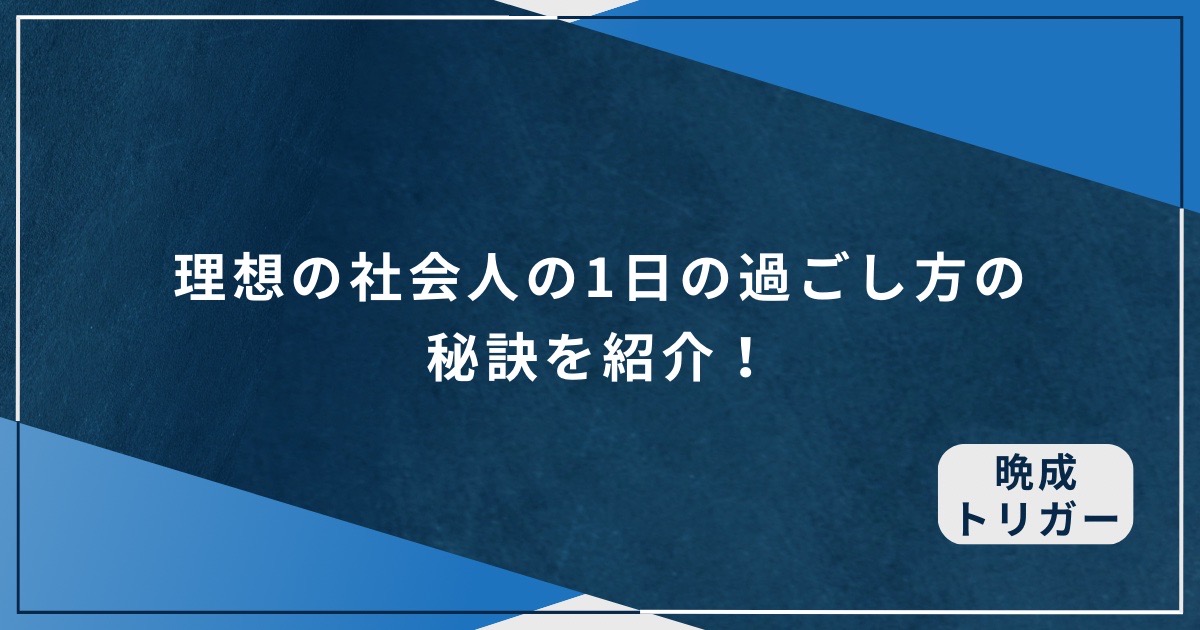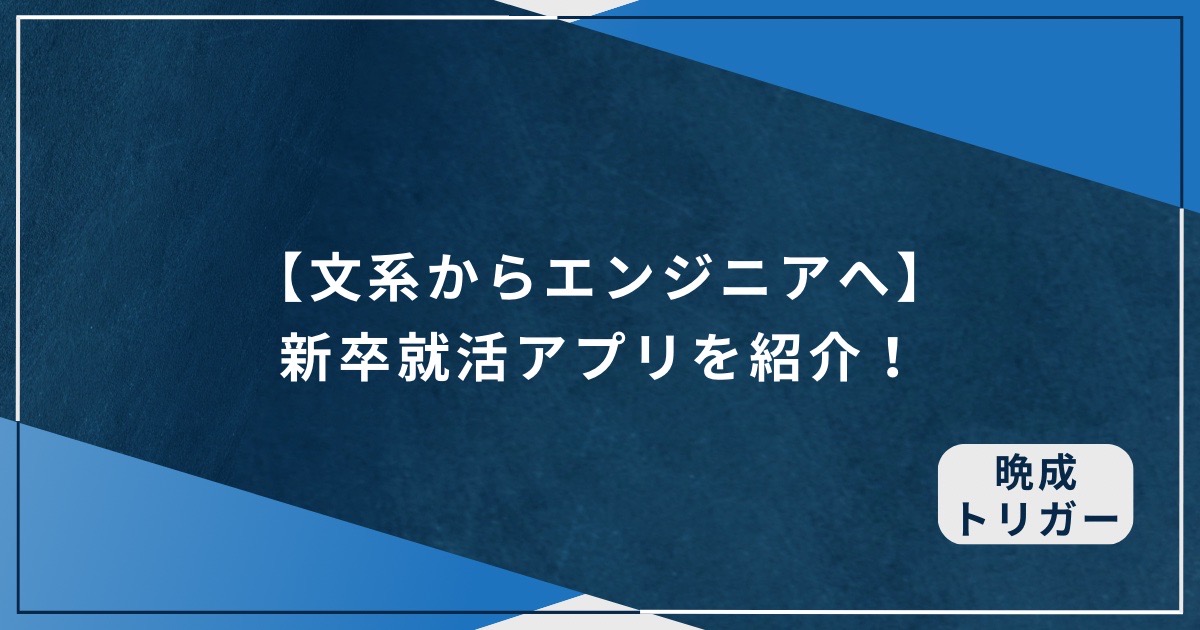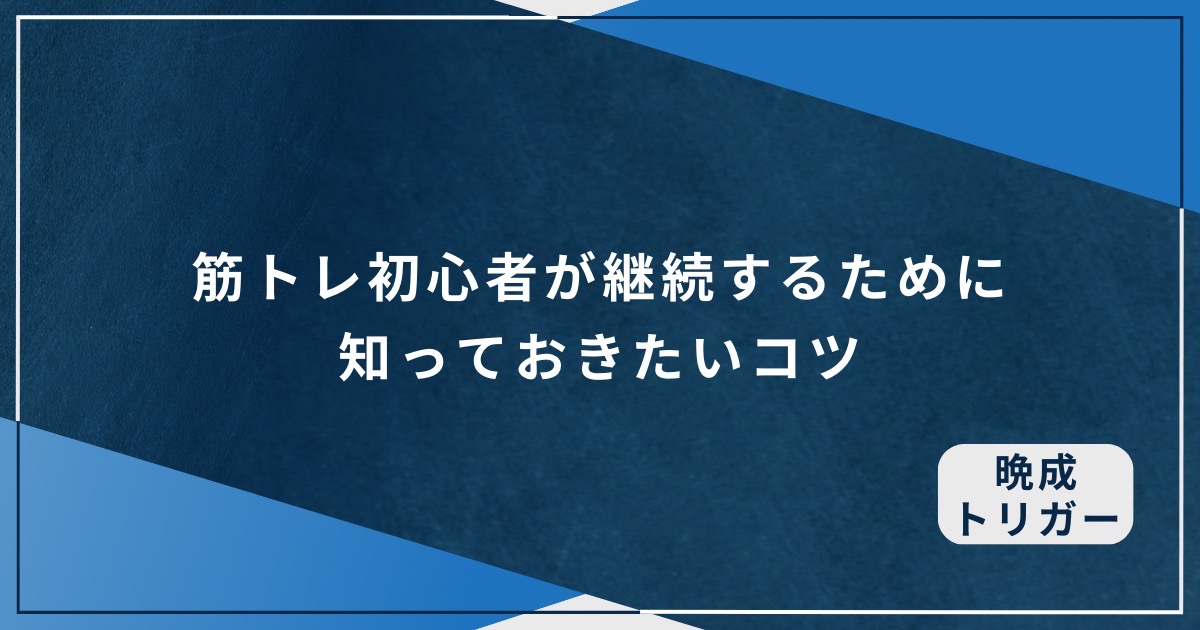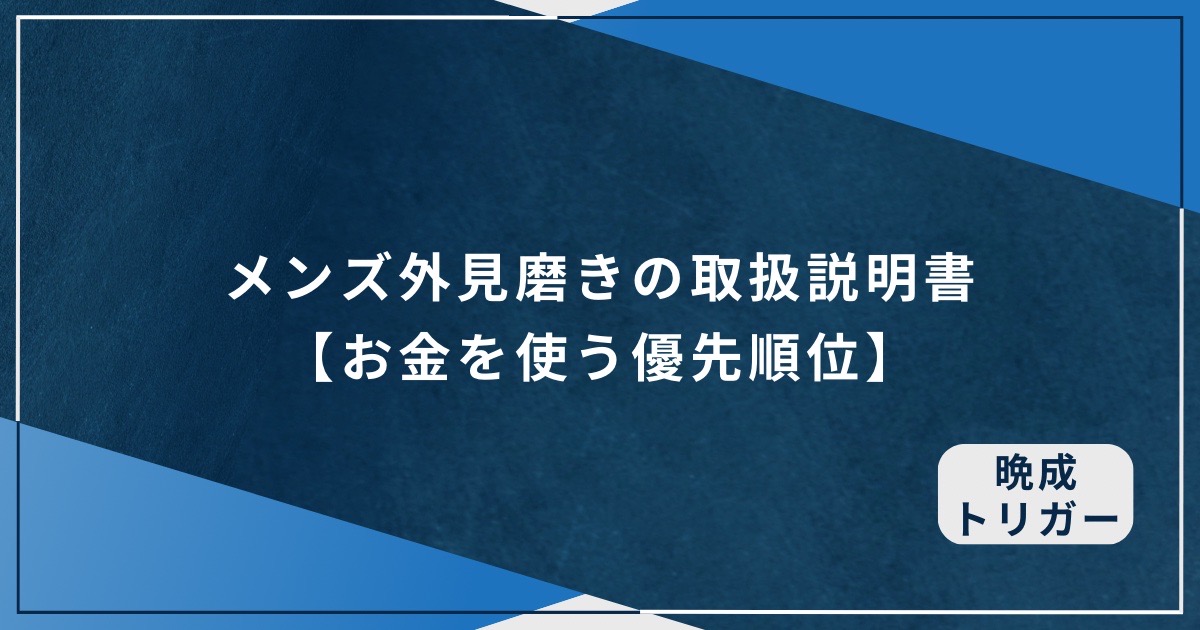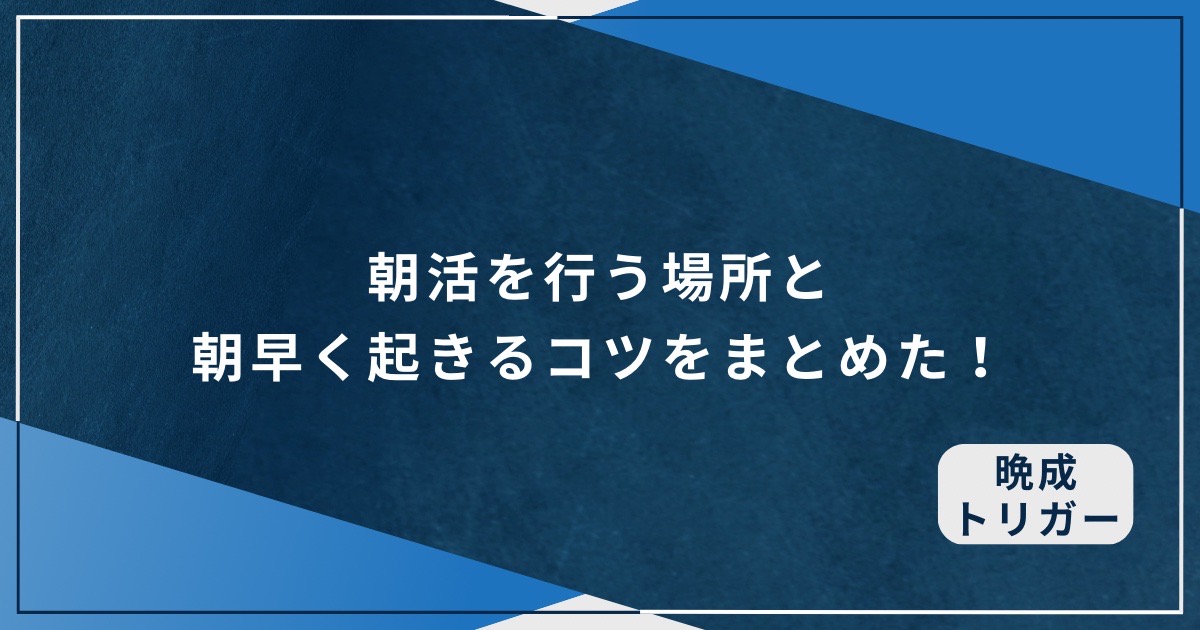大学生の友人の作り方を知りたいです。
こんなお悩みに答えます。
この記事では、「大学で友人を作るタイミング」を紹介します。

授業・単位から、就活など情報が必要なシーンは多くあります。
最後まで読むと、友人を継続させるコツも知ることができます。
ではさっそく見ていきましょう。
大学で友人がいないデメリット
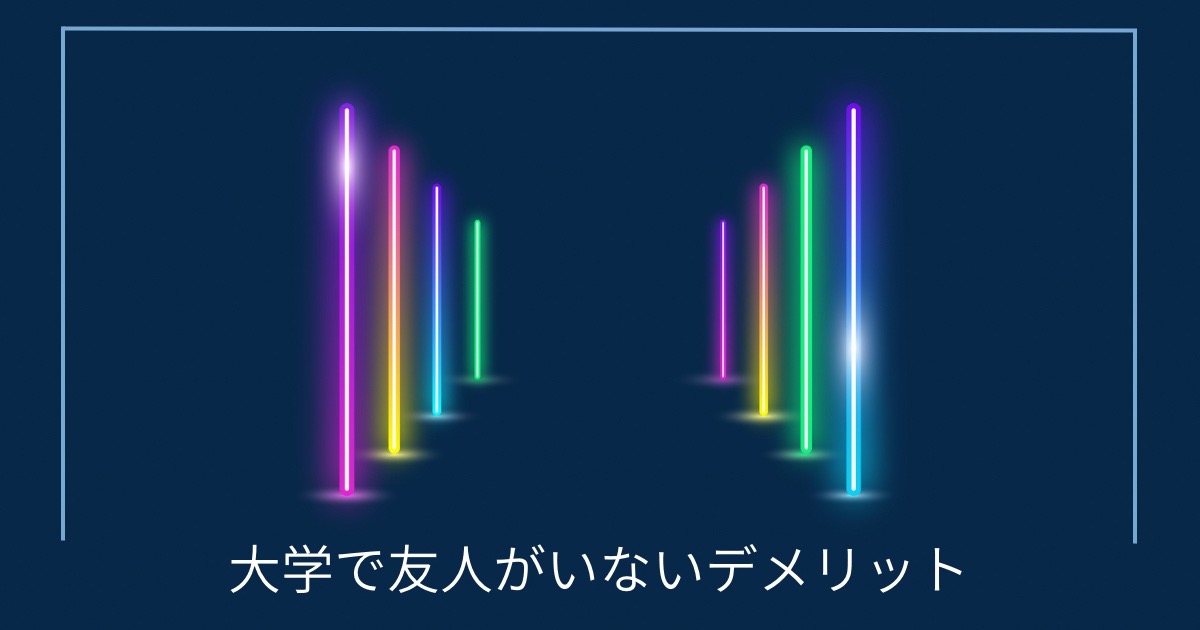
まずは、大学で友人がいないデメリットを紹介します。
- 孤独感がある
- 情報交換ができない
- 思い出が残らない
- コミュ力が低下していく
1つずつ解説していきます。
友人がいないデメリット①:孤独感がある
大学に友人がいなければ、孤独感を感じるかもしれません。
誰か知っている人がいないかと、探したくなることもあります。
偶然友人に会ったときは、本当に嬉しいです。
せっかく大学まで来ているならば、誰かと話したくなります。
基本的に1人が好きな人は少ないのは、間違いありません。
孤独感に苛まれるとき
- 周りに知ってる人がいない
- 部屋でSNSを見てるとき
- やることがないとき
ただ、1人でいることは完全に悪いことではないです。
むしろ、孤独でいる時間を作ろうと心がけるべきでしょう。
誰かと遊ぶのは、週に1〜2回がちょうど良いくらいです。
1人でいるからこそ、やりたいことができます。
いや、1人だからこそ、何かをしようという思考になるかもしれません。

友人がいないデメリット②:情報交換ができない
情報交換ができない場面を2つに分けて紹介します。
情報交換ができない場面
- 授業・単位関係
- 就職活動関係
順番に紹介します。
情報交換ができない①:授業・単位関係
大学に友人がいないと、情報交換がしづらいです。
意外と、1人では気づかないことを教えてくれる人がいます。
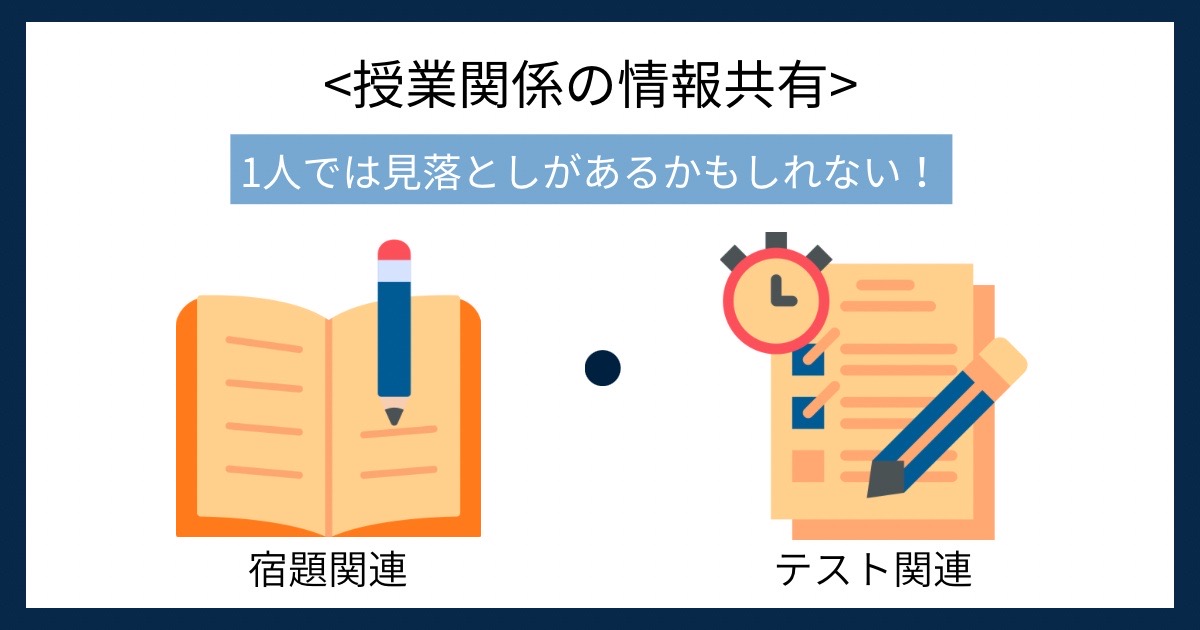
宿題の答え合わせや休講情報など、1人では厳しいこともあります。
もちろん、テスト関係の情報も大切な情報です。
テスト関係の情報
- テストの日程
- テスト範囲・内容
- テストする教室
また大学の授業では、ペアワークも多数存在します。
必修の授業で、横の子と会話する授業は結構ある印象です。
極力ペアワークの授業を避けてきました。
それでも、いくつかの授業ではペアワークがありました。
初回の授業が始まる前に、横の子に話しかけていました。

情報交換ができない②:就職活動関係
就職活動を1人で乗り越えるのは、かなり大変なことです。
自分ならば、正直厳しいかなと思います。
実際に、周りの友人に助けられたことがあります。
就職活動のゴールは、納得した企業に入ることです。
ですが、そのためにやることは際限なくあります。
- 自己分析
- テスト勉強
- OB訪問
- 企業分析
- 面接対策
これを全部1人でやると、途中で息が詰まりそうになります。
同大学の助け合える友人がいるだけで、最後まで頑張ろうと思えました。
辛い時期に話し相手がいるだけでも、ありがたいです。
もう一度就活をするならば、絶対に一緒に頑張る友人を見つけて始めます。
もちろん、行きたい会社があるなら、先輩探しも大事です。

友人がいないデメリット③:思い出が残らない
僕が大学生の頃は、旅行よりもブログが好きでした。
そのため、友人と遠出をすることは珍しいです。
誰かと遠出するのは、年に2回くらいな気がします。
それならば、1人で自由で出かける傾向にあります。
そんな僕でも、友人とのしょうもない日々の出来事は、思い出です。
大学生活の思い出
- 学校帰りのラーメン
- オールした記憶
- 遠出して遊んだ思い出
- バンジージャンプした経験
- 学校の授業関連の会話
過去を振り返ってみると、誰かといたときの記憶が蘇ってきます。
思い出とは、1人ではなく、誰かと何かをした経験なのでしょう。
もちろん、大学の友人だけである必要なしです。
中学校・高校の友人と遊ぶことも思い出になります。
ただ、どこで遊ぶかいくつかの選択肢を持っておきましょう。

-
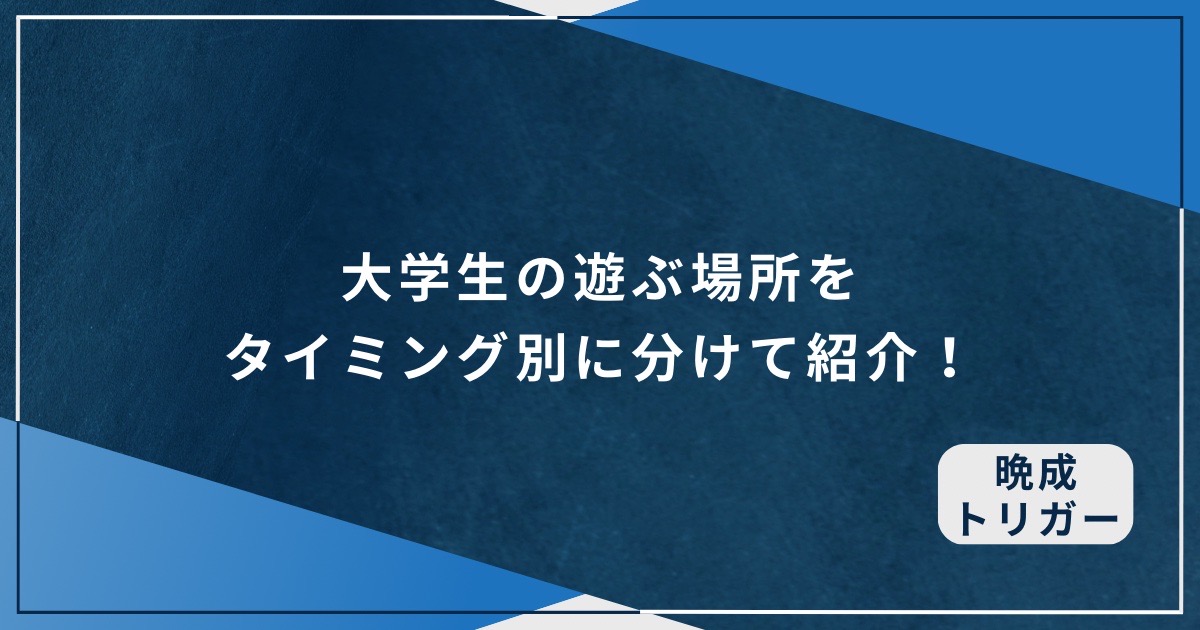
-
大学生の遊ぶ場所を紹介!
こんなお悩みに答えます。 この記事では、「おすすめの遊び場所」を紹介します。 最後まで読むと、1人で出かける場所も知るこ ...
友人がいないデメリット④:コミュ力が低下していく
大学に友人がいないと、コミュニケーションが減ります。
実際に大学で一言も話さずに、帰ることもありえます。
関係ないですが、ブログのために大学行ってたときはそうでした。
コミュニケーション力は、どこに行っても大切と言われます。
1人で生きていける人はいないため、仕方がない気がします。
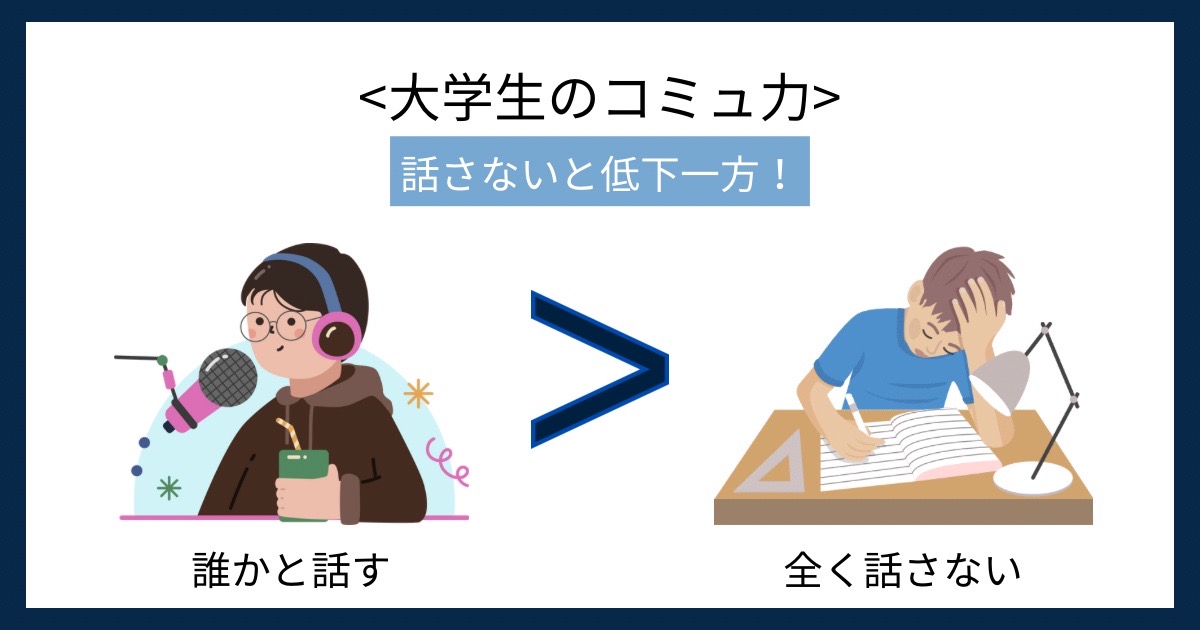
そもそも、大学で話す機会はどれくらいあるのでしょうか。
周りと話す機会
- 授業・宿題関連
- サークル・部活関係
- ゼミ関係
- プライベートな話
大学の友人は、まずは世間話がメインで始まります。
そこから、踏み込んだ話をする仲になることが多いです。
いきなりプライベートの話する人はいないはずです。
少しずつ話すようになって、仲良くなっていきます。

大学で友人を作るタイミング

次に、大学で友人を作るタイミングを紹介します。
- 入学式・新入生説明会
- 初回の授業前・後
- 新入生歓迎会
- 部活・サークル
- ゼミ活動
順番に解説していきます。
大学で友人を作るタイミング①:入学式・新入生説明会
一番最初に同級生と会うのは、おそらく入学式になります。
その機会に話すことは、SNSで知り合った人くらいでしょう。

それならば、新入生説明会のときに周りの人に話しかけましょう。
まだグループ形成もしておらず、1人でいる人も多いです。
話しかけるのは、早い段階の方が絶対に良いです。
そこまで友人を作りたい訳ではないなら、焦る必要はありません。
ただ、大学生活において、友人関係は大切なものであります。
焦って適当に声をかけるのも、個人的に違う気がします。
せっかく時間をかけて参加するならば、知り合いを作りましょう。
周りも声をかけようか悩んでるからこそ、行動できるのは強いです。

大学で友人を作るタイミング②:初回の授業前・後
僕は、基本的に初回の授業で声をかけるようにしてました。
授業前に声をかけた人が、結果として友人になりがちです。
大学で仲の良い人の大半は、授業前に声をかけた人です。
色々声をかけた内、偶然同じ学部だった人とは今でも仲良くしてます。
話しかける内容
- 学部などの自己紹介
- 受ける授業について
- 高校の部活の話
特に体育の授業の前だと、かなり話しやすい雰囲気があります。
体育の授業があるならば、初回に声をかけてみるのをおすすめします。
実際に、3回生の後期から仲良くなった子もいます。
些細な共通点が合うと、簡単に仲良くなれるのが大学生です。
だからこそ、色々な人に声をかけてみるのが大切です。

大学で友人を作るタイミング③:新入生歓迎会
サークルの新入生歓迎会で、新しい友人ができるかもしれません。
興味のある部活・サークルに、1人で来ている人もいます。
サークルの新歓事情
- 4・5月メインである
- 放課後中心に行われる
- 先輩の奢りかもしれない
大学生活の最初に出会ったサークル仲間と最後まで過ごすことも多いです。
人数が多いサークルほど、顔見知りは増えていきます。
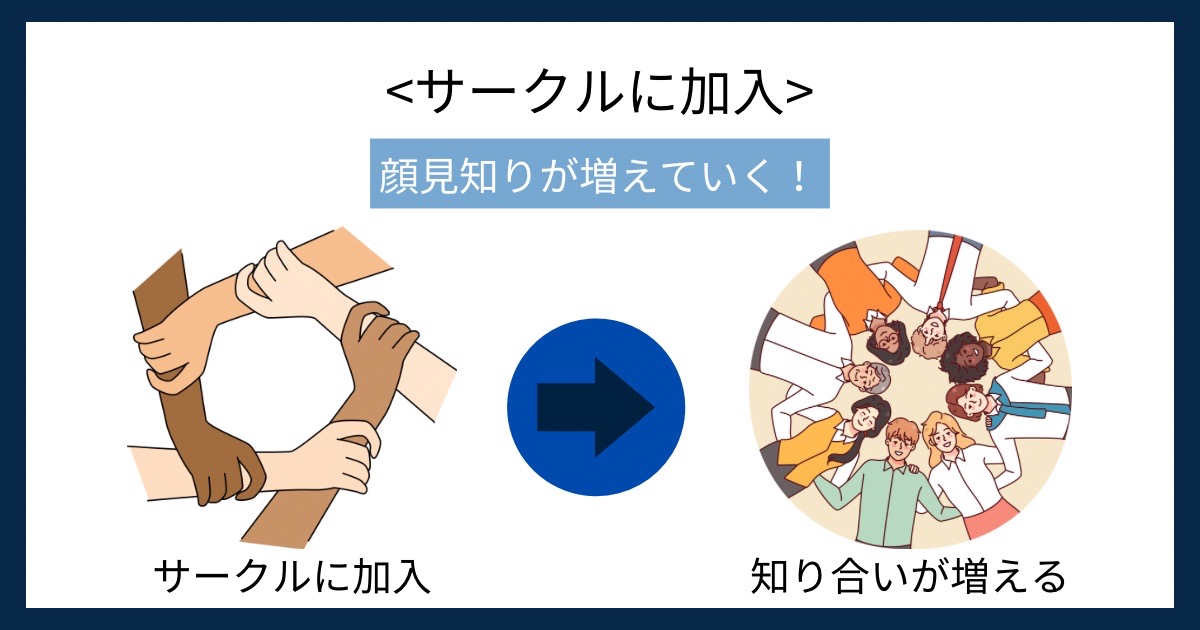
ただ、顔見知りが増えるだけで、深い付き合いができないかもしれません。
それでも、知り合いがいない大学生にとって、有難いことではあります。
僕は、浅くて広い付き合いは、正直苦手です。
しっかり前見て頑張ってる人と、深く長く付き合っていきたい人間です。
これは性格によって分かれるため、とりあえず参加してみるのもOKです。

大学で友人を作るタイミング④:部活・サークル
おそらく、部活・サークルのメンバーと一緒にいる時間が一番長いです。
そのため、部活・サークルに入ると、友人を作りやすいでしょう。
- サークル:週に1〜2回
- 部活:週に3〜5回
活動日数に違いはありますが、友人の作りやすい環境は変わらないです。
最初は、人が集まっている所に参加してみるのが良いです。
部活の方が、一緒にいる時間が長く、深い仲になれそうです。
どちらにせよ、自分の理想の生活に合わなければ、辞めるかもしれません。
それならば、仲の良い友人を作るために、サークルに参加でもOKです。
実際にサークルに行ってる人は、10%と言われています。
そこまで難しく考えることなく、参加しても良いかと思います。

-
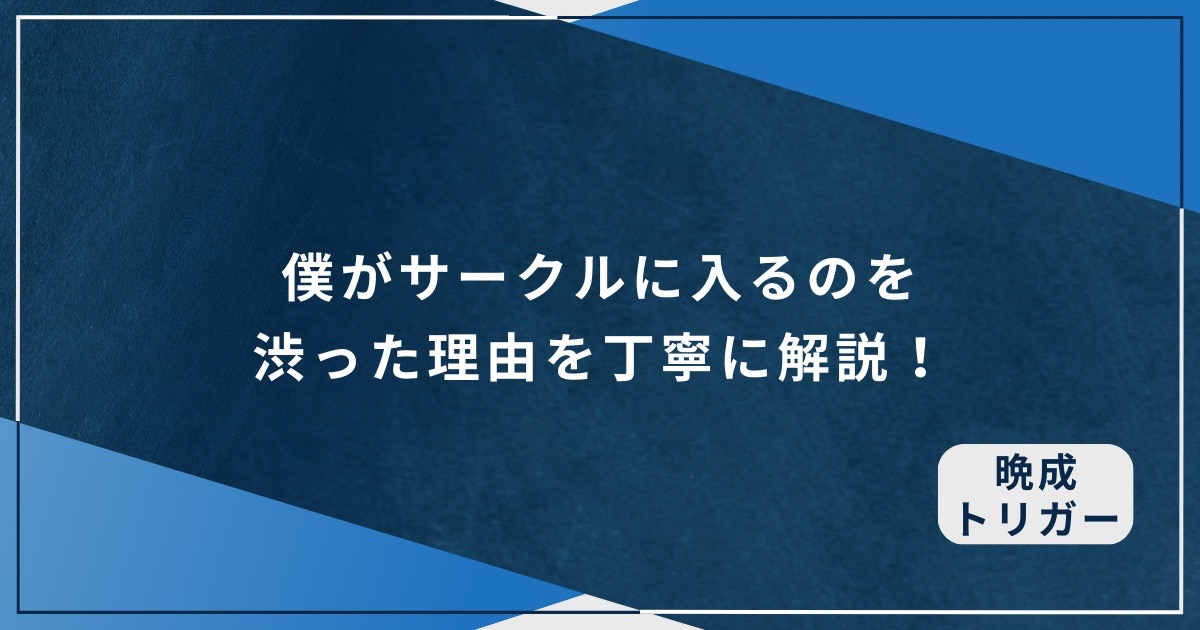
-
サークル加入を渋った理由
こんなお悩みに答えます。 この記事では、「サークルに加入するメリット」について紹介します。 最後まで読むと、僕がサークル ...
大学で友人を作るタイミング⑤:ゼミ活動
大学3年生から本格的にゼミ活動が始まります。
そのタイミングで、新しい友人を作ることができます。
それまでに、他の友人は作っておきたいのが本音です。
ゼミに入るときに、〇〇の知り合いという風に話題にできます。
共通の知り合いがいるだけで、最初の話題に困ることはほぼありません。
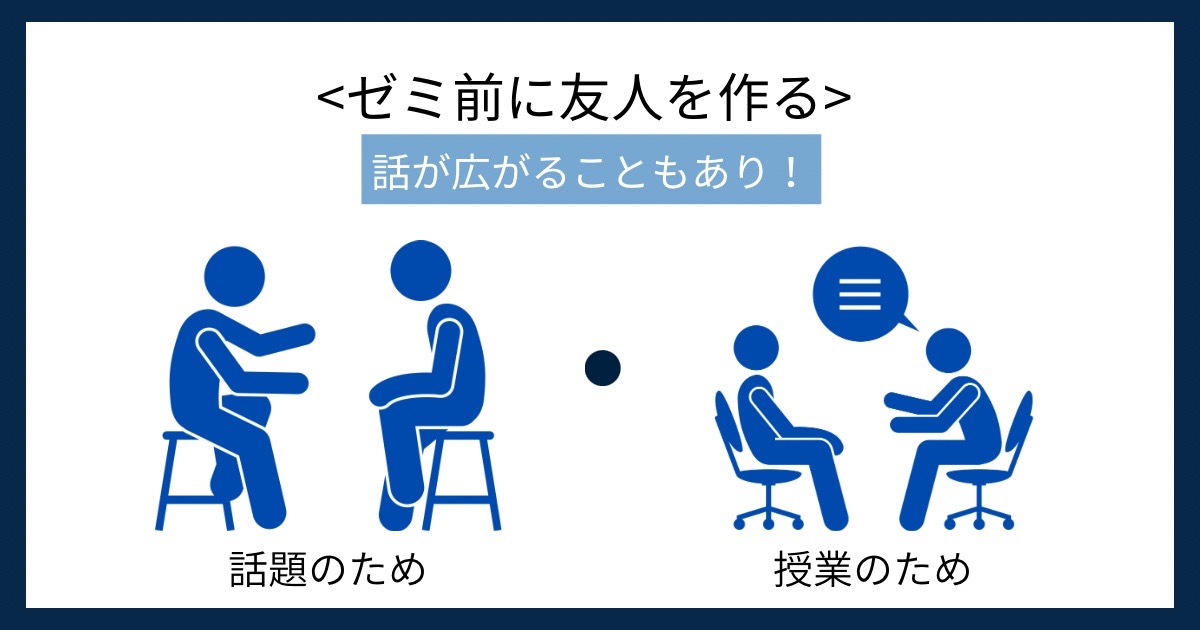
それに2年間知り合いなしで、大学生活を送るのは寂しいです。
自分から声をかけたら、意外と仲良くなれると思います。
大学生なんて、最初はみんな1人が多いです。
就職活動もあるため、ゼミ以外の友人と情報共有できる状態にしましょう。

大学外で友人を作るタイミング

次に、大学外で友人を作るタイミングを紹介します。
- アルバイト・インターン
- 他大学のサークル
- SNS・マッチングアプリ
- 習い事
順番に解説していきます。
友人を作るタイミング①:アルバイト・インターン
大学外で友人を作るならば、アルバイトが一般的です。
また、インターンに参加すると、様々な人と関わることが可能です。
インターンのメリット
- リアルな職業体験ができる
- ガクチカに使える
- お金がもらえる
社員さんと同等の仕事の分、早めに社会経験を積むことができます。
そのため、就活の際にも、周りよりも有利な状況で挑めます。
ちなみに僕は、長期インターンは参加してないです。
もちろん、アルバイトでも、人脈を広げることはできます。
むしろ、気楽に遊ぶならば、アルバイトの方が良いです。
同世代が多いバイトを選ぶと、困ることはありません。
学校外でも、気が合えば、友人を作ることは可能です。

友人を作るタイミング②:他大学のサークル
自分の大学のサークルではなく、他大学のサークルに参加もOKです。
ただ、全部のサークルが外部生を受け入れてる訳ではないです。
そういうサークルを、インカレサークルと呼びます。
色んな大学の人が混じってるサークルならば、問題はありません。
ですが、1つの大学がメインならば、話題に困ることも抑えましょう。
インカレの探し方
- ネットで探す
- メンバーに声をかける
- チラシから連絡する
インカレ自体は問題ありませんが、自分の生活と合うか確認しましょう。
生活が合わないと、結局サークルに顔を出すのが億劫になります。

インカレサークルは、場所が固定されないことも多いのが事実です。
そのため、移動をストレスを感じる人にはおすすめできません。
ただ、その分、色々な人と関われる環境ではあります。
多くの大学生と関わってみたいならば、インカレがおすすめです。
周りも大学生が多く、話題に困ることも少ないでしょう。

友人を作るタイミング③:SNS・マッチングアプリ
外部で友人を作るならば、SNSを利用するのも可能です。
SNSだからこそ、事前にどんな人か分かる部分もあります。
怪しい感じなのには、警戒をしておきましょう。
また、マッチングアプリも同様におすすめです。
異性だけでなく、同性とも仲良くなれる可能性を秘めています。
マッチングアプリの例
- ペアーズ
- with
- タップル
とりあえず、人数が多いものを選ぶと会える可能性も高まります。
こだわりがない人は、有名なものを利用するのが良いです。
ただし、月額数千円かかることもあります。
正直バイト数時間分と思えば、そこまで高くないです。
それでも、お金を払ってまで出会いを求めてない人もいるでしょう。

友人を作るタイミング④:習い事
習い事をすると、共通の話題ができやすいです。
共通の話題があれば、心の距離も近づきやすい傾向にあります。
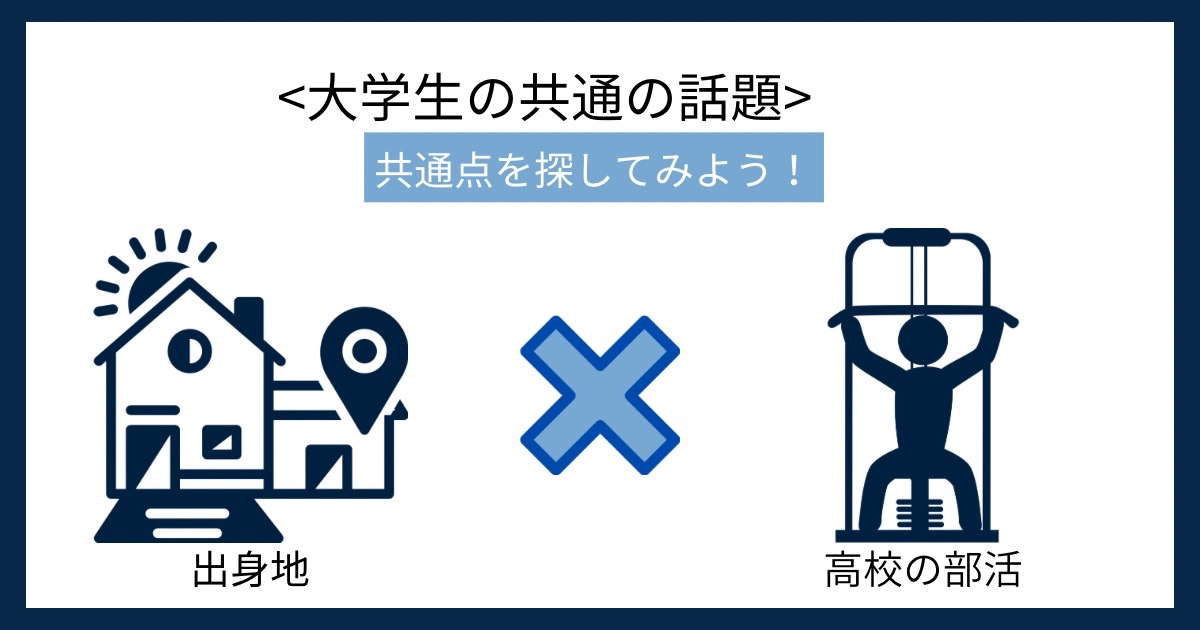
当たり前のことですが、似ている人の方が安心感が生まれます。
そういう面で、同じ習い事をしているだけでも、話すきっかけができます。
- 英会話
- テニス
- 水泳
- ボルタリング
大学生になってから、新しいことを始めることは問題ありません。
これまで熱中した経験がない人こそ、新しく始めて欲しいです。
大学では、勉強だけしていても評価されにくい環境です。
最低限の勉強もしつつ、他のこともしてる人が良いイメージです。
高校生までの勉強だけができればOKとは、少し違います。

友人関係を継続させる方法

最後に、友人関係の継続方法を紹介します。
- 前提:続かない方が多い
- 相手の生活を尊重
- 自分から連絡してみる
- 先に予定を入れておく
- 本音で話す人を決める
1つずつ解説していきます。
前提:続かない方が多い
大学の友人は、長く続かないことの方が多いです。
実際に、僕も大学外でも遊ぶ友人は、片手で数えれるくらいです。

自分からLINEを交換しても、結局連絡しなくなることが多いです。
大学はそういう場所と割り切ってると、気楽に友人ができるでしょう。
3人ほど、社会人でも仲の良い友人がいれば十分でしょう。
声をかけるだけと思えば、難易度が下がる気がします。
声をかけること自体は、そこまで苦手な印象がありません。
話すことが苦手な僕でも、できることです。
むしろ、友人を作るよりも継続させる方が難しい印象です。
そのため、友人関係を継続させる方法を紹介していきます。

友人関係の継続方法①:相手の生活を尊重
大学生以降、1人になる機会は多くなります。
そのため、周りを頼って生きてきた人は、少し大変になります。
当たり前ですが、全部自分の人生です。
友達には友達の人生があり、様々な予定があります。
なのに、相手の生活に干渉しすぎるのは良くありません。
相手に干渉すぎない方法
- 相手に期待しすぎない
- 見返りを求めない
- 自分だけの時間を愛する
自分の生活に相手が介入しすぎるのは、嫌なことです。
それを反対に、友人にしていないか再確認しましょう。
干渉しすぎないのが、長い交友関係に繋がりがちです。
両方が同じ距離感で安心感を感じてるからこそ、続いていきます。
それでも離れていくときは、仕方がないと思いましょう。

-
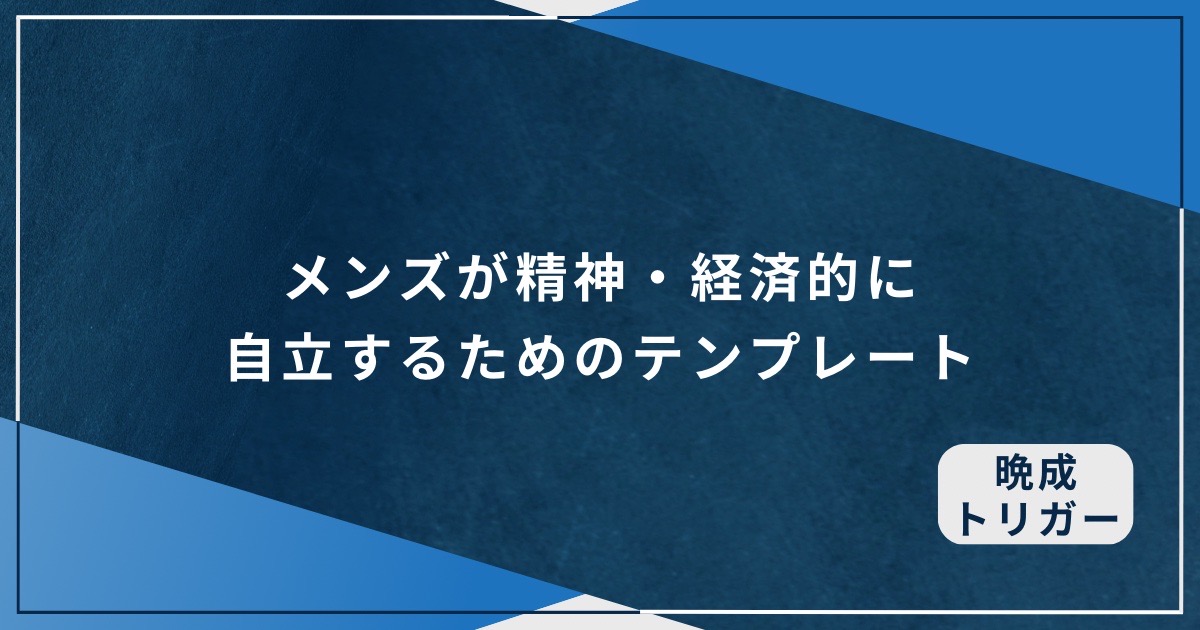
-
メンズが自立するためには
こんなお悩みに答えます。 この記事では、「精神的に自立している人の特徴」を紹介します。 最後まで読むと、今すぐにできるこ ...
友人関係の継続方法②:自分から連絡してみる
友人関係を継続させるためには、たまには連絡することが大切です。
連絡の仕方
- LINE
- 電話
- 友達の友達に伝える
連絡することは面倒ですが、遠距離になると、離れていく一方です。
会えない距離でも、たまには自分から連絡してみましょう。
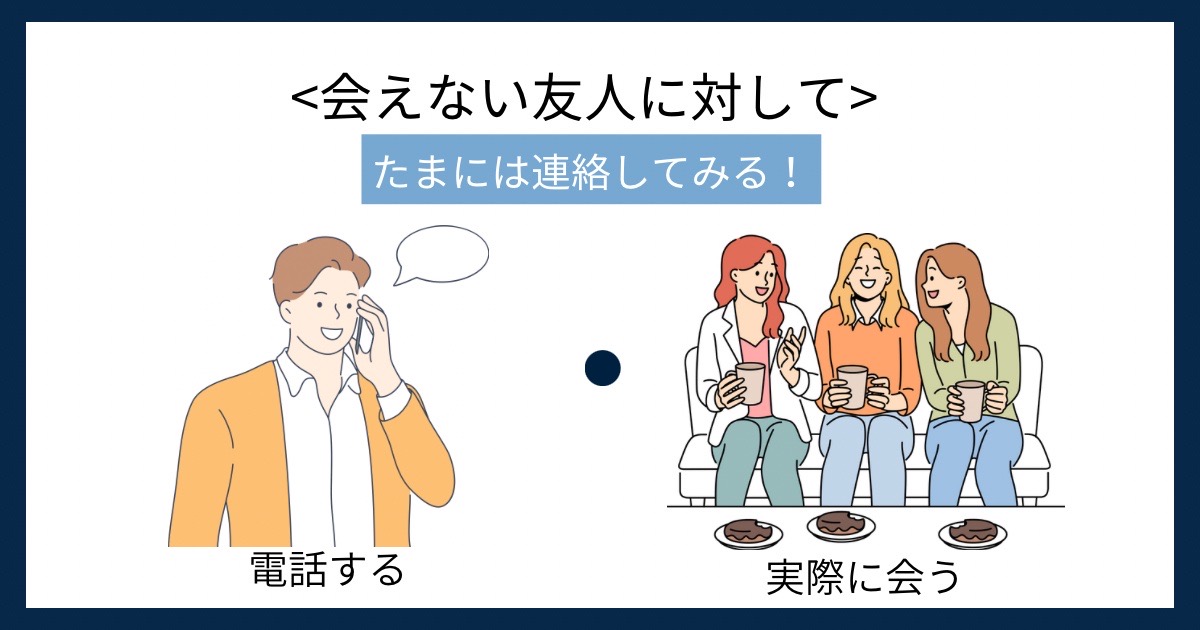
久しぶりに会うからこそ、色々な話をすることができます。
昔のことから、最近の面白い話など、意外と盛り上がりがちです。
毎日会っていたら、同じ話題になりがちです。
3ヶ月から〜半年に1回くらいを目安に連絡してみましょう。
時々連絡が来るからこそ、交友関係が続いていくかもしれません。

友人関係の継続方法③:先に予定を入れておく
友人と会う予定は、早い段階に入れておくのがおすすめです。
基本的に、最低2週間前には決めておきたいと思います。
当日に遊べる友人がいるなら、気にする必要はないです。
個人的に、先に予定を決めておかないと行く気がなくなりがちです。
まぁ、そういう人間が一定数いて、そういう人と仲良くしてます。
友人と遊ぶルールの例
- 毎週○曜日の午後
- 1週間に1〜2人会う
- 3ヶ月に1回連絡を取る
各個人の性格によって、ルールを変えてみてOKです。
ルールを決めているからこそ、安定して友人関係を維持できます。
会いたいときに会うのは、必ずしもおすすめできません。
恋人ならまだしも、友人に対してわがまますぎは、好ましくありません。
たくさん会ったら、仲良くなれるという訳ではありません。

友人関係の継続方法④:本音で話す人を決める
友人関係を継続させるには、本音を話す人を決めるのがおすすめです。
全友達に時間を割くとなると、自分の時間は無くなっていきます。
大事にする人の選び方
- 何かを頑張ってる人
- 価値観が合う人
- 時間を割いて会いたい人
自分の人生だからこそ、自分主体で生きましょう。
大切な人を決めるからこそ、今ある関係を大切にできます。
結局、服も数着しか着ないように、人間関係も同じです。
少し悲しいことかもしれませんが、大切にするとはこういうことです。
浅くて広い関係だと、最終的に誰も残らないかもしれません。
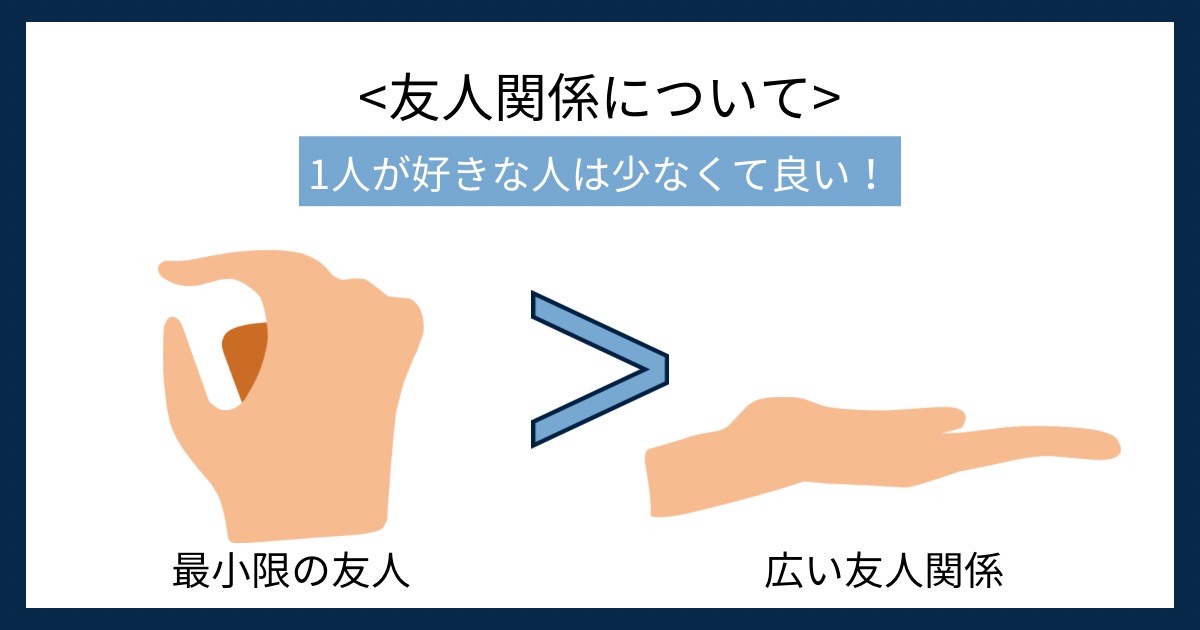
どうせ悩んでいても、最終的には、年を取って死んでいきます。
それならば、自分が大切にしたい人を大切にする方が幸せです。
自分が満足してるなら、気にしなくてOKです。
割り切って生きる方が、人生気楽に生きることができます。

まとめ:求めすぎず話しかける!

「大学で友人を作るタイミング」を紹介しました。
友人作りで困っている大学生は少なくありません。
基本的に自分から話しかけることが大事です。
もちろん、求めすぎて話しかけるのは、相手に引かれてしまいます。
気軽に話しかけて、偶然の出会いを大切にしていきましょう。